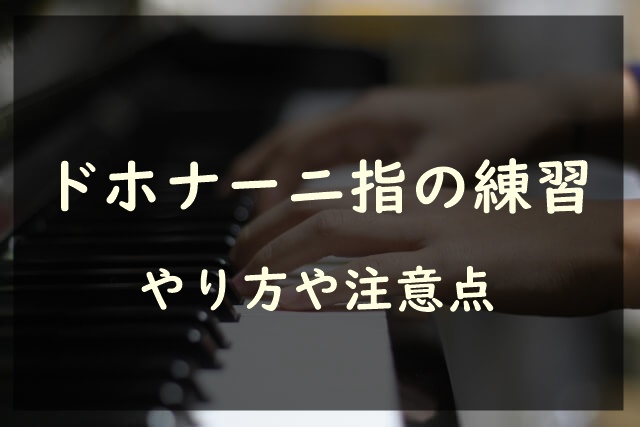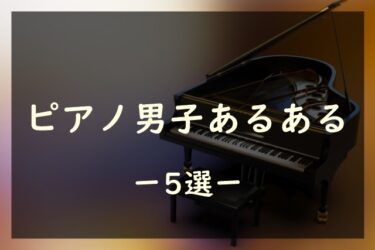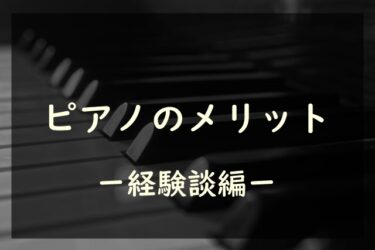こんにちは、おとぎです。
「ピアノの初心者をそろそろ卒業できそう」
「もう1段階上の練習がしてみたい」
そういった人たちにおすすめなのが、ドホナーニ指の練習です。
今回はそんなドホナーニ指の練習について、基本情報をまとめました。
良かったら参考にしてください。
ドホナーニ指の練習は、4~5年前にプロのピアニストさんの話を聞いて知りました。
知ってからの4~5年間、ほぼ毎日この指練習をやってきて感じたことも多いです。
そんな経験などをもとに書いているので、良かったら参考にしてください。
ドホナーニ指の練習について
まずは、ドホナーニ指の練習の特徴についてです。
代表的なものを2つ紹介しています。

目的は指の独立
この教材の目的は指の独立です。
指の独立が上手くいっていないと、たとえばこんなことが起こります。
・薬指と一緒に小指も動く
・和音を弾くと弱い音がある
・速く弾くところで1音抜ける
つまり、こういったことの改善を目指す教材ということですね。
後半は、20年以上ピアノを弾いていても、難しいものがあったりします。
なので長く使えるというのも、特徴の1つですね。
保持音を使った練習
気になる内容について、たとえばこんなものがあります。
- 右手の1・2・5番の指でド・レ・ソを押さえる
- その状態のまま3・4番の指でミ・ファを交互に弾く
- これを左手も同時にやる
難易度が上がってくると、鍵盤を押さえる指が1本で動かす指が4本になったりもしますね。
ちなみにこういった練習は、保持音を使った練習と言ったりもするので、良かったら覚えておいてください。
なので、人によって弾き方が全然違ったりもしますね。
【やり方】効果的な強さ・速さで
練習する際は、こんな点がポイントになります。
・指に意識を集中させる
・腕や手首をあまり動かさない
・難しく感じる強さ・速さで
・最初は片手ずつでOK
あくまでも指の練習が目的なので、意識はとにかく指へ!という感じですね。
また、強弱などを指定してない曲が多いため、プロのピアニストさんでも強さや速さの意見が分かれます。
YouTubeとかを見ていても、
「ゆっくり弱く弾かないと意味がありません!」
と言っている先生の1つ下にある動画で、プロのピアニストさんが力強くガンガン弾いてたりもしますね。
たとえば僕だったら、ある程度強くだと簡単にできたので、mpくらいの強さで少し遅めに弾いています。
やはりピアノの上達に必要なのは、できないことの反復練習です。
そしてこれも練習なので、目指しているのはピアノの上達ですよね。
なので、人それぞれ上達につながる練習をすることが重要だと思います。
もしかしたら、ドホナーニもそんなことへの意識で、強弱の指定をしなかったのかもしれませんね。

【注意点】無理はしない
- やり過ぎはケガの原因に
- 短時間で集中して行う
- 重要なのは継続
ケガには注意しましょう。
慣れない手の形をしたりもするので、やり過ぎは手を痛める原因にもなります。
ピアノの練習で重要なのは、長期間の継続です。
ピアノの上達をあせる気持ちも分かりますが、練習は短時間で集中してやるようにしましょう。
おすすめのやり方-練習のルーティーンに
- 練習の最初に数分やる
- 忙しい時はこれだけやる
- 挫折の防止にも効果的
おすすめなのは、この教本を練習の最低目標にすることです。
ドホナーニ指の練習は、ゆっくり弾いても1曲数分で終わります。
なのでたとえば、
「練習の最初にやる」
「忙しい・気が乗らない時もこれだけはやる」
のように、あらかじめ決めておくのがいいですね。
気が乗らない時もピアノを数分触ることで、急にやる気が出たりもしますね。
そんな感じで、こういったものを最低目標にすることは、継続にも効果的なので覚えておきましょう。
こんにちは、おとぎです。 家での時間が増えたのをきっかけに、ピアノを始めてみた人も多いですよね。 しかし練習が続かず、挫折してしまう人も多かったりします。 そこで今回は、ピアノの練習が続かない[…]
【まとめ】ドホナーニ指の練習で差をつける
最後にこの記事のまとめです。
・目的→指の独立
・内容→保持音を使った練習
・効果的な強さ・速さでやる
・ケガには注意
・練習の最低目標に設定する
ドホナーニ指の練習は、やはり短期間で効果が期待できるものではありません。
ですが長い期間継続することで、効果を実感する時が必ず来ると思います。
なので、もし他の人と差をつけたい時は、このドホナーニ指の練習も選択肢の1つにしてみてください。
記事はこれで以上です。
他の記事では、僕のピアノ経験についてまとめていたりもします。
こんにちは、おとぎです。 近年、ピアノ男子という言葉を聞く機会が増えてきました。 多くの人が憧れたりもしますが、本当に良いことばかりなのか気になりますよね。 そこで今回は、ピアノ男子のあるある[…]
こんにちは、おとぎです。 「ピアノを趣味にするメリットって?」 「大人からじゃ遅いかな?」 趣味で音楽といえばピアノ、なんてイメージの人も多いと思います。 そんなピアノのメリットを調べ[…]
良かったら参考にしてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。